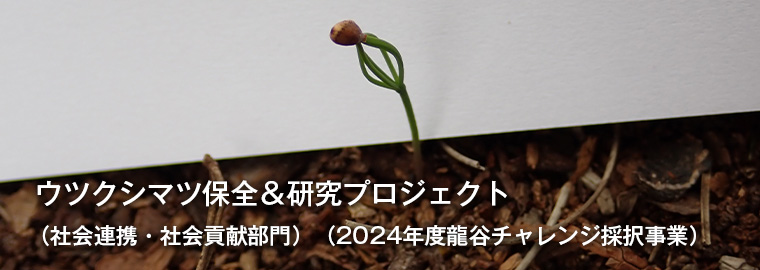(1)事業の概要
滋賀県湖南市には国の天然記念物に指定されている「平松のウツクシマツ自生地」がある。ウツクシマツはアカマツの天然変種で、幹に主幹がなく、1本の根元近くから枝分かれし、樹冠は傘を逆さにした特異な形態をしている。この独特な形をしたウツクシマツが群生し、天然更新をしている所は「平松のウツクシマツ自生地」のみで、平安時代の伝説が言い伝えられていたり、江戸時代には東海道五十三次の名所にもなっていたりした。本事業では、そのような歴史ある天然記念物を保全、研究することを目的とする。
(2)事業実施に至る経緯と背景
平松のウツクシマツ自生地では、社会環境の変化や、松枯れ被害の拡大によりウツクシマツが枯死し、数を減らしている。ピーク時に264本あったウツクシマツは2021年に90本以下になってしまい、このままではウツクシマツが減失しかねない状況になっている。松枯れ被害防止のために薬剤散布を行っているが被害を無くすことは困難なため、既存の個体を守るだけでなく、新たに芽生えを増やそうといった活動が近年積極的に行われている。私達は、その活動に参加するとともに、ほかに何か保全につながる活動ができないかと考えた。
(3)事業実施項目
(1) 天然更新の促進
松は、腐葉土層のような栄養がある場所では発芽・生長しにくく、地表が見えるような痩地で発芽・生長する。平松のウツクシマツ自生地では、地表に生えている笹や、松の落ち葉が放置され、分解されたことによって栄養豊富な腐葉土層が10㎝以上堆積している(ガスや電気が主流ではなかった時代は、落ち葉などは竈や焚火などにくべていた)。そこで、地掻きと落ち葉掻きと言い、自生地に溜まった栄養のある土や、地表付近に生えている笹・落ち葉などを全てかきだし、松の生育に適した環境をつくる作業を行った。土砂崩れ等を考慮し、区画を決め、鍬を使って腐葉土層や笹を取り除き、その下にある痩せた土を地表に出した。
(2) 芽生えの撮影
新たに芽生えを増やす活動である地掻き作業や、杉の伐採が功を奏し、作業を行った場所から多くの芽生えを確認できた。この芽生えは、100本程度見つかった。しかし、実生は確認されているが、芽生えのその瞬間を記録した動画が無く、この嬉しさを共有する手段が無い。このような広告媒体があればうまく、再生に目処がついたことを示す格好の動画材料になるのではないかと考えた。
撮影を行う中で、地掻き作業を行ってからどれくらいで芽生えるのか分からない点や、ピントを合わせられない点など問題点が見つかったため、芽生えてすぐの個体を撮影した。また、ウツクシマツ自生地近隣に落ちているウツクシマツのものと思われる松ぼっくりから種を採取して植え、撮影を試みたが、適切な土壌や気温を用意できず、芽生えの撮影はできなかった。
(3) 遺伝子検査の依頼の実施
ウツクシマツの科学的価値を高めるために遺伝子解析を行おうと考えた。専門性が高く、多額の資金が必要なため、森林総合研究所へ赴き解析の依頼を行った。その結果、森林総合研究所よりさらに松のゲノムに詳しい林木木育種センターがあることと、普通のアカマツのゲノムが韓国の研究グループによって解析結果が出ていることを教えていただけた。また、林木育種センターで引き受けていただけない場合は、森林総合研究所で解析してもらえることとなった。また、樹形の形には、植物ホルモンが関わっていることが多く、それを調べる手もあると分かった。
解析の際は、方法にもよるが、100個体ほど必要になる。新鮮な松の葉をチャック袋に入れて冷蔵で送れば解析していただける。必要な個体数が多く、圃場にどのくらいの個体があるかなど確認しなければならない。
(4)事業の成果
- 地掻きや落ち葉掻きに参加することで、作業を実施した個所から松の芽生えを確認出来た。笹が生い茂る地面を鍬で10㎝ほど掻くので体力と時間が必要になり、参加人数が多いほど作業できる区画が増える。私達は、2~3人で1区画を担当した。
- 地掻きや落ち葉掻きなどの保全活動を行った区画に芽生えた実生をインターバル撮影することで、芽生えを増やす保全活動が実を結んでいると湖南市に再認識してもらうとともに、湖南市のホームページやYouTube等に広告媒体として載せられるような動画を提供し、広報の手助けとした。また、まだどのような形となるかは決まっていないが、掲載された際には、近隣地域の住民にウツクシマツの価値を再認識してもらうとともに、より多くの人にウツクシマツを知ってもらう機会となる。
- 森林総合研究所へゲノム解析の依頼、相談をしたことで今後どのように解析するかということと、解析に必要なものが明確になった。ウツクシマツは劣勢遺伝子で、樹形で判断するには5年かかり、また、矮性か高性の判断がつくのに7年かかる。今後、林木育種センターか森林総合研究所にて遺伝子の解析を行って頂くことになるが、解析された暁には、実生の段階から遺伝子解析を行い選定できるようになる。
(5)今後の課題と展望
今回の事業での課題は、ウツクシマツの実態について分からないことが多く、自生地での芽生えを撮影できなかった点と、森林総合研究所(宮澤さん、上野さん)より松のゲノムに詳しい林木育種センター(平尾さん)を知らなかった点、松のゲノム解析に100個体ほどのサンプルが必要であり、圃場に植えられているサンプルがどれほどあるか確認できていない点である。
今後はまず、鉢での芽生えの撮影を行い、それが成功したら自生地での芽生えに挑む。さらに、森林総合研究所より教えていただき、すでに連絡を取っている林木育種センターに赴き、依頼を行うとともに必要なものや、どのくらい時間がかかるかなどの話し合いをする。また、圃場へ行き、サンプリングできる個体がどのくらいあるのか確認する。
また、園芸用の「多行松」や森林総合研究所内や全国にウツクシマツと似たような変種があるのでそれらの遺伝子も解析するとともに、仏教大学の特性を活かし、全国のお寺に変わった松がないか調査し、ウツクシマツとの関係性を調べる。
さらに、森林総合研究所で行われている不定杯誘導によって1個体から大量に増殖させ、盆栽など園芸化して知名度を高めることも考えていきたい。
(6)事業実施を通じて見出された特長
- ポイント1「とにかく足を運ぶ」
- ポイント2「保全活動は活動後の成果が重要」
- ポイント3「専門家の話を聞くと活動の幅が広がる」
活動団体情報
代表者
東 采佳
連絡先
REC事務部(京都)
主な連携メンバー
湖南市、森林総合研究所
主な活動地域
平松のウツクシマツ自生地(滋賀県湖南市平松541番地)